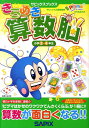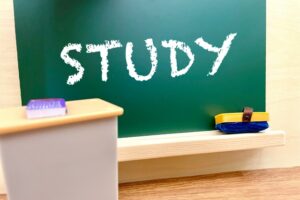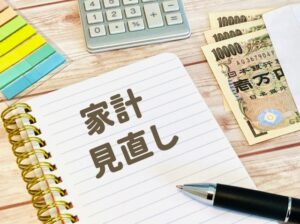はじめに
住んでいるエリアは教育熱心な家庭が多いので幼児の頃から複数の習い事をさせるのが当たり前。
文武両道を実現している家庭もある一方、あれこれ習い事をさせられて死んだ魚の目のような子もいます。
幼児の頃から習い事をさせられて伸びている家庭があるものの、自分自身が嫌々習い事をさせられていたので習い事をさせるのは慎重になっています。
うまくやれている家庭はお子さんを乗せるのが上手なのでしょうね。
習い事を始めてどこを目指す?
プロを目指すのであれば幼児からやっていた方が良い習い事もある一方、小学校から始めても追いつく場合もあります。それはそのときにならないとわからない事かもしれませんね。
だから幼児の頃から習い事を始める家庭が多いのでしょうね。
我が家は習い事を通じてプロを目指しているわけではないので幼児の頃からやらせる必要性を感じてません。プロの選手になりたいと思ったらうちには生まれてきていないと思います。
住宅ローンを完済したらわりとすぐに子供を授かったのでもしかしたらお金に不自由したくない子たちなのかなとは思いましたね。
習い事は本人が興味を持ったらいつでも始めればいいと思っています。
子供の習い事の目的は本人が頑張りたい事を応援したい、大人になってからも「心の拠り所」を見つけられたらいいです。
だから本人が興味を持った時がチャンスだと感じています。
【回顧録】幼児教室で感じた憂鬱
実際上の子を幼稚園受験のため幼児教室に通わせていた時には本当に本人は嫌そうにしていました。そして親の私から見ても担当の先生はひどかった。
一言で言うと近所の普通のおばさんがマニュアルで予習してレッスンを進めるかたち。先生に不信感があるので講師の求人を見たら驚くことに学歴不問。
これだったら一流大学出身の夫が家で教えた方がコスパ良くないか?
なので講師は誰にでもすぐなれますのでわざわざ通う必要はありません。
教室には赤ちゃんの時から通っている子もいたけど、教室で良く出てくるものしか対策していないようにも見えました。

4月生まれだというのに数字も1から10まで言えない、あまり人と器用に関われる子ではない。
赤ちゃんの頃から幼児教室にお金を使う家庭は(そこの家庭だけかもしれないけど)教室に通う事によって安心感を得たいだけの家庭にも見えました。
小さい頃から幼児教室に通う意味ある?
これだったら家で通信教育の教材をやれば十分。そう思いましたね。
それに教室や塾に通っていなければ自分たちでやらなくてはいけない事が増える。
課金して安心するぐらいなら、課金する余裕はあるけれど、課金しないで不安感からあれこれ対策した方が我が家には合っていると感じました。
↓別館ブログにも書いたけど具体的な対策方法はこちらです。

もっとまともな先生が他にいなかったのかしら?
で、幼児教室の回顧録を書くと止まらなくなりました。

シリーズ6で終わるので興味がある方は最後まで読んでみて下さいね。
そんな感じなので我が家は必要最低限の習い事をさせています。下の子はまだ3歳なので何も習い事をさせていないし、本人が興味を持ったドリルをやらせるだけ。
上の子が家庭学習をしているのを見て勝手にやりたがります。

そして上の子は自分からやりたいと何カ月も懇願してきた習い事と家庭学習でポピーやドリルをやらせています。空き時間にやればいいだけなので通塾よりも遥かに時間のやりくりも楽で費用も格安です。

低学年からの入塾のデメリット3つ。
ぺたほめの藤田敦子さんは佐藤ママの対抗馬としての位置づけの方のようで、過度な早期教育を否定されています。
先日藤田さんがアップしていた記事。

低学年からの入塾のデメリットの理由について藤田さんは
①親子の時間が減ること
②勉強嫌いになる可能性あること
③自己肯定感が低くなる可能性が高まること
と説明しています。
①親子の時間が減ること
塾の授業や宿題で遊ぶ時間が減り、親子で過ごす時間も短くなると言います。そして多く遊んできた子供は絶対に自己肯定感も高くなり、頑張ることを惜しまない子に育つと言います。
→納得です。
だって沢山子供たちを遊ばせていたら旅行先でテレビ局の人たちの目に留まり、取材を受けましたもん。
このとき勉強だけできる子に育てなくて良かったと心から思いましたね。頑張るのを止めようとしても止められない子たちに育ったと言えば伝わるかな?
②勉強嫌いになる可能性があること
低学年までは友達と遊ぶ時間も大切。学校はコミュニケーション養成場。
→同様の考えなので子供は早くから児童館や保育園のイベントにでかけたし2歳前には保育園に預けるようにしました。結果、人との関わるのが好きな子たちに。

家庭で保育園と同じ教育を施そうと思っても難しいです。だって親しかいないから。
友達との関わりで学べることも多くあります。
友達と遊べなかったり、仲間外れにされたり、なじめなかったりが『塾のせい→勉強のせい→勉強嫌い』となる可能性も小さいからこそ多くなる可能性があります。
学校にまだ慣れていないのに、塾の時間や宿題など負担が大きすぎて、結果勉強は大変なものとなって嫌いになる可能性もあります。
→私も子供たちには負担のないように家庭での勉強習慣を身に付けさせたいと思っています。短期間で効率よく身に付けさせようとなったら小学校に上がる前は基礎学力を身に付けるだけで十分。
小学校に入ってから子供たちの様子を見ながらギアを入れてペース配分を考えていけば良いと考えています。
③自己肯定感が低くなる可能性が高まること
塾に行くと模擬テストなどで順位や偏差値も出ます。塾では成績順で座らせたり、成績でクラス分けなどもあります。小さい時から人と比較されて、自分はできないと思う機会が増えます。
親も宿題などさせなければが増えるので、「ガミガミ」も増えます。
それらの結果、子どもの自己肯定感が低くなります。
→我が家では他人と比較しない子育てを実践していました。・・・にも関わらず幼児教室のクラスでは同級生と比較されて辟易。で、幼児の頃から教室に行ったら子育てに悪影響って結論なのですよね。他の習い事も先生がうまくやれる人でなければ同様。
私が感じている早期の習い事のデメリット
私も低学年からの入塾のメリットはあまり感じていません。というのも私が中学年から親から無理やり公文をやらされ、仕方なく始めましたが、幼児の頃から始めた友達に追いついてしまったのです。

友達に追いついてしまったというのは一例なのでみんながそうなるとは限りませんが、この経験もあるので私自身は幼児の頃からカリカリ勉強する必要なんて全くないと胸を張って言えます。
幼児の頃からやっていた習い事の時間分が無駄になるのだから、もっと親子で楽しく過ごす経験の方が大事だと感じますね。
幼児からの過剰な勉強は家庭のブラック企業化の第一歩。ブラック企業はいくら長時間一生懸命働いても安い給料でこき使われるだけ。
それと同様に子供本人が成長する前に無理に勉強させられたら心が壊れてしまうんですよね。
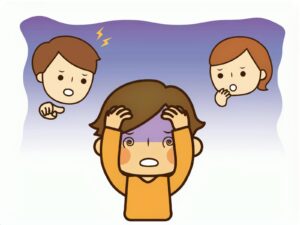
私の場合、公文だけではなくて部活も途中から追いつきました。あとから遅れてとある運動部に入りましたが、最終的には部内で一番の成績でした。
いつ始めたかではなく本人のやる気が問題。子供たちのやる気が持続する環境づくりと基礎学力だけは身に付けさせてあげたいです。
教育費にお金をかける家庭と勉強時間が長い子が賢くなるというのなら誰も子供の教育で苦労する人なんていないと思います。
一つの単元をマスターするまでの標準学習時間があったとしたら、最低限その標準学習時間は勉強する時間が必要。
その上でペース配分を考えられる家庭が強いと感じます。我が家は勉強ができる子になっても本人が潰れてしまったら子育ては失敗だと考えています。
↓昔親戚にもそう言われたし、大人になってからは親戚が言った事が正しいと感じるよ。
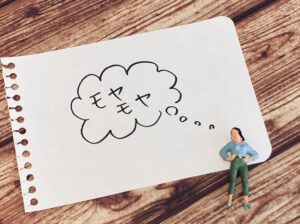
だけど本人が潰れても学歴さえ身に付ければそれでいいというのならこの限りではありません。
社会性がない子に育ち、親子関係が悪くなるのは確実だけど。